子どもにいちばん身につけてほしいのは、どのような力ですか?
「コミュニケーション力」「リーダーシップ」「語学力」などなど、いろいろありますね。
一つにしぼるのは難しいかも知れませんが、私だったら自己肯定感と答えます。
「これがあれば幸せに暮らしていける」とすら言われているほど大事なものです。
自己肯定感が高い子どもは「困難にぶつかっても、あきらめない心をもち、乗り越えていく力を十分に発揮できる」といわれています。
・自己肯定感の高い低いって性格の差なの?
・自己肯定感はなぜ必要なのか
・海外と比べて日本人は自己肯定感が低い
・自己肯定感をそだてるのは「勇気づけ」
・「勇気づけ」のやり方
クリックできる目次
そもそも自己肯定感とは何?
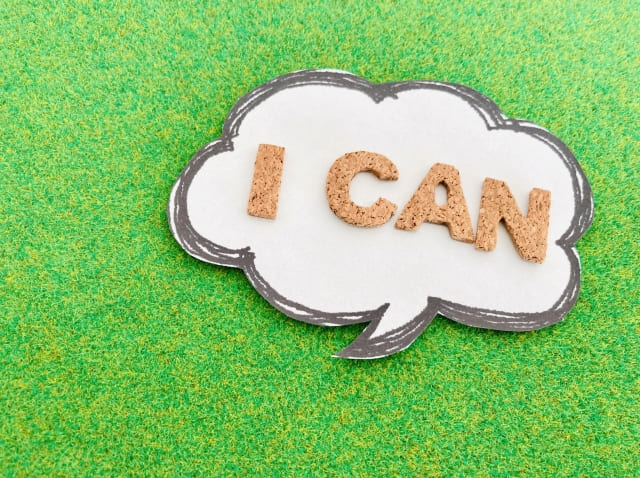
そもそも自己肯定感とは、どのようなものなのでしょうか?
「自分はすごい!」と思えることではありません。

自己肯定感とは、自分の短所や弱点も受け入れ、自分を認め、肯定する気持ちのことです
つまり「ありのままの自分でいいんだ!」「このままでいいんだ!」と思えることです。
自己肯定感が低い人は「自分なんてダメな人間なんだ」と思いがちで、何かに挑戦する前から「どうせダメだろう」とあきらめグセがついている人もめずらしくありません。
自己肯定感の高い人の特徴
反対に自己肯定感の高い人には、次のような特徴がみられます。
・自分を価値ある存在だと思えている
・自分の魅力を知っている
・困難にぶつかったときも、それに立ち向かう勇気をもてる
・失敗したときにも自分を責めすぎず、立ち直りが早い
自己肯定感はなぜ必要?

なぜ自己肯定感が必要なのでしょうか?
アンケート結果からも、自己肯定感が高い人はそうでない人に比べ、失敗にくじけない心を持っていることが明らかになっています。
また、ストレス耐性があることもわかっています。
ご存知のようにストレスは、うつ病をはじめ、肉体的な病にも深くかかわってきます。

そのため、自己肯定感が高いと健康を保ちやすいとも言われています
逆に自己肯定感が低いと、挑戦する心を持てないために、せっかくの能力も活かしきれずに宝の持ちぐされとなりかねません。
自己肯定感の低い人は、他にも「落ち込みやすい」「他人の評価を気にしすぎてしまう」「必要以上に人と比べてしまう」などの特徴があります。
以上のことから、自己肯定感の高さは子どもの頃だけでなく、大人になってからも重要な要素となります。
自己肯定感が高いのは生まれもった性格なのか?
「ポジティブ」とか「へこみやすい」などについては

あの人はもともと、そういう性格だから
と認識されがちです。
たしかにそういう側面もあるかも知れません。
しかし、性格のみが自己肯定感の高さを決めるわけではありません。
子どもとのかかわり方次第で自己肯定感は高めることができるのです。
日本人は自己肯定感が低い

内閣府により、7か国の13~29歳の若者へのアンケート調査が5年ごとに行われています。
調査項目に自己肯定感に関する「自分自身に満足している」という質問があります。
これに「そう思う」と回答した日本人はどれくらいいるのでしょうか?

う~ん、低いっていうなら…20%くらい?

正解は、なんとたったの10.4%なんです

え~!そんなに低いの!?
「どちらかといえばそう思う」という回答と合算しても45.1%です。
ちなみに最も高いポイントだったアメリカは、87%が「満足している」と答えています。
他の国もすべて7割以上が「満足している」との回答でした。

どうしてこんなに大きな差が出ているのでしょうか?
1つは子どもたちのおかれている環境にあるとも言われています。
「できればマル、できなければバツ」といった結果主義。
過程や挑戦する姿勢よりも、結果で評価されてしまう。
「できたあなたはスゴイ、できなかったあなたはダメ」と、ありのままを肯定されることが少ないからだと言われています。

点数重視・テスト主義の弊害ともいえそうですね
「ほめる」より「勇気づけ」が大事な理由

だからこそ、せめて家庭ではありのままの子どもを受け入れ、大切にしていきたいですね。
では、子どもが自己肯定感をもてる子育てとは、どんなものでしょうか。

ほめることでしょ?

実はそれがちょっと違うんです
ベストセラーとなった「嫌われる勇気」で、多くの人が耳にしたアドラー心理学。
それによると「ほめる」よりも「勇気づけ」が必要といわれています。
ほめる行為はもちろんいけないことではありません。
しかし、ほめる子育てには次のようなリスクもあります。
・ほめられるであろうことしかチャレンジしなくなる
・ほめられないとやらなくなる

だから「ほめる」よりも「勇気づけ」が大切なのです
勇気づけとは「できる」というイメージをプレゼントすること

じゃあ勇気づけって具体的にはどうすればいいの?
アドラー心理学では以下のように示されています。
勇気づけとは困難を乗り越える力を与えること。
たとえば子どもが転んでしまったとき、すぐに手をさしのべるのではなく、「痛いね。でもがんばって立とう。きみならできるよ」と、あげる感じです。

たしかにこんな言葉をかけてもらったら、「がんばろう」と思えます
もうひとつ、例をあげてみましょう。
テストの結果がよくなかった子どもに対し「もう!またこんな点だったの!」というのではなく、「よし、次こそはがんばろう!」と声をかけ、克服する力・チャレンジする力を与えること。
これが勇気づけとなります。

勇気づけには「こうすればいい」という正解はありません
自分が子どもだったら「どうしてもらったらうれしいか」「どうしてもらったら力が湧いてくるか」「どうしてもらったらやる気と自信が生まれるか」
これを基準に考えて、声をかけてあげてください。

僕ならきっとできる!
子どもが、こういうイメージができるような言葉をプレゼントしてあげることです。
パパママ自身も勇気づけよう

とはいえ、「子どもに言いすぎてしまった」「なんであんな言い方してしまったんだろう」
こんな自責の念にかられたことは誰しもあるはず。

大丈夫!そんな経験、あなただけではありませんよ!

そんなときは、こうやって自分を勇気づけましょう!
「自分なりに精一杯やっている」
「すべてにおいて完璧なママ(パパ)でなくたっていい」
「自分だって子どもと一緒に成長中」

まずはがんばっている自分を認めてあげてくださいね

勇気づけはそこからスタートです
興味のある方は上手なほめ方・叱り方もご覧ください。
まとめ
最後に、今回の記事をおさらいしておきます。
自己肯定感の高い人とは「自分を肯定する心」「自分を好きという気持ち」をもち、弱点や短所も含め、ありのままの自分を受け入れられる人です。
言いかえると、「自分を価値ある人間だと信じている人」であり、次のような特徴があります。
・失敗からの立ち直りがはやい
・失敗しても必要以上に自分を責めすぎない
・ストレスに強い
反対に自己肯定感の低い人として以下が挙げられます。
・「どうせ何をやってもダメだ、うまくいかない」とチャレンジ精神を失いがち
・失敗したときに立ち直るのが遅い
そして自己肯定感は子育てのなかで与えていくことができるものです。
・大切なのは困難を乗り越える力を与える「勇気づけ」
パパママが、子どもにどんな言葉をかけてあげるか。
子どもは、声掛けひとつでどんどん成長していきます。
小さければ小さいほど、その影響は大きいものです。
言葉と笑顔で子どもを勇気づけていきましょう!


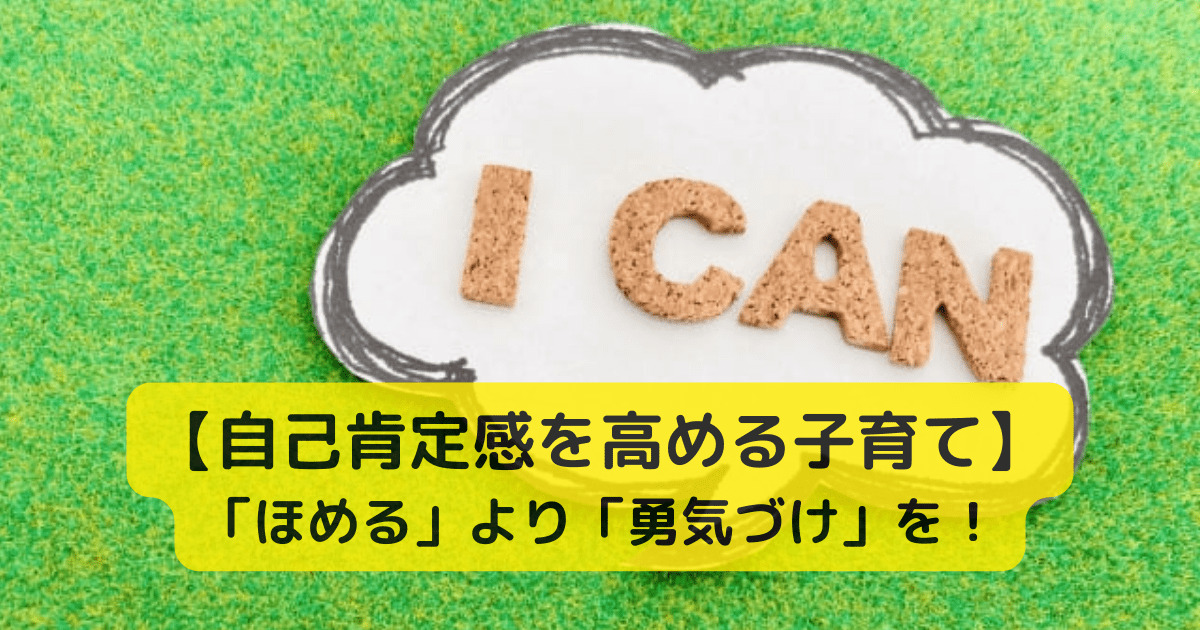
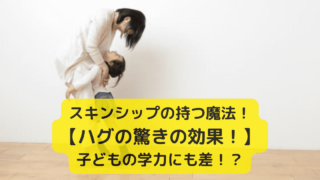
コメント